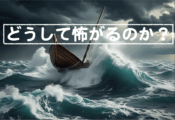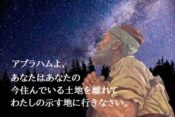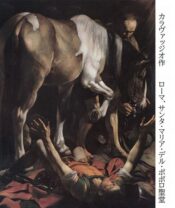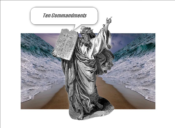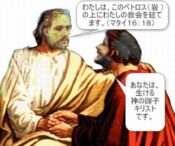イエスに従うとは?
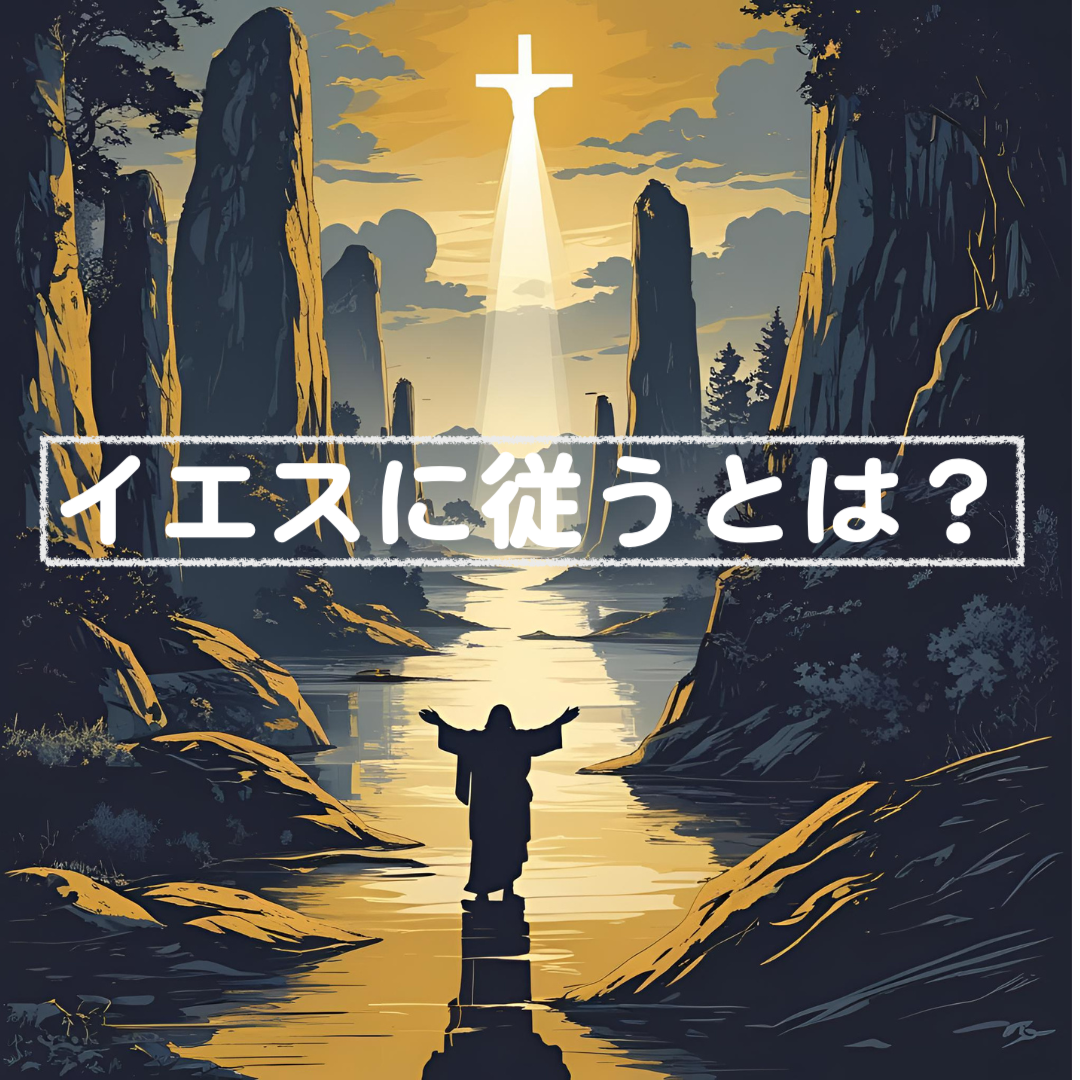
「イエスに従うとは?」
マタイの福音書8章18-22節
クリスチャンとはどういう人のことでしょうか。教会に通っている人、聖書を読んでいる人、善良な生き方をしている人・・・様々なイメージがあるかもしれません。これらはどれも大切なことでしょう。しかし信仰とは、単なる思想や、心の中で教えを信じることにとどまりません。
信仰とは、イエスに従うことです。イエスに従う歩みをし、生活をしていくことです。今日の箇所には、イエスに対して不十分な応答をした2人の人が登場します。
1. 熱狂的な律法学者
1人目は律法学者です。彼は「先生。あなたがどこに行かれても、私はついて行きます」(19節)と言っています。「どこに行かれても」とは、なかなか立派な告白です。ところが、それに対するイエスの返答はやや冷たいように聞こえます。
「狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。」(20節)
聖書 新改訳2017©2017新日本聖書刊行会
「人の子」とはイエスのことを指しますが、さすらう習性のある狐や鳥にさえ安らぐ場所があるが、自分にはゆっくりと休む場所もない。第一、いろんな問題を抱えた人たちが、ひっきりなしにやってくるわけです。イエスは一人ひとりに愛をもって関わられるわけですから、その体力、気力の消耗はどれほどのものだったでしょうか。その、イエスについて行く覚悟が本当にあるのか? そのことを問われたのです。
この律法学者が、どれほど真剣にそのことを考慮していたかは、実は彼の発言から伺うことができます。彼はイエスを「先生」と呼びましたが、マタイの福音書において、イエスを「先生」と呼ぶのは、まだ本当の弟子ではない人たちです。弟子たちは、イエスを「主よ」と呼びかけます。
この律法学者は、自分の研究、経験、知見に基づいて、この方は「先生」と呼ぶに値する立派な方だと思っていました。おそらくイエスの奇跡も目の当たりにしてきたのでしょう。だから実際についていけば、もっと多くのことが学べる、見れる。彼の気持ちが全面的に嘘だったというわけはないでしょう。しかし、本当の意味でイエスに従っていくことが、どういうことであるかまでは考えが至ってなかった。この律法学者は、決心を急いでしまったのです。
キリスト教信仰は、よくわからないけれどとりあえず信じる、ということではありません。あるいは単に知的に理解しているということでもない。信仰とは、イエスに従うということです。イエス・キリストの語られること、生き方に倣っていくこと。神の子として生き、天に国籍、本拠地がある者としてこの世で生きていくことです。裏返せば、この地上には真の国籍、拠点はないということ。この世においては旅人、寄留者であるということです。ですからこの世の常識とは異なる前提、基準を持っているということです。信仰者として生きるというのは、今の自分の生き方を「ちょっと良くしたり」、補強してくれるようなものではありません。信仰はアクセサリーではない。そうではなく、自分の生き方を変えて、方向転換をして、イエスに従うということなのです。この世の常識や、世間の当たり前にではなく、イエスに従う歩みだからです。
ローマ人への手紙12章2節にはこうあります。
聖書 新改訳2017©2017新日本聖書刊行会
この世と調子を合わせるのではなく、神のみこころ(何が良いことで、神に喜ばれるか)を基準として生きるのです。律法学者は、このクリスチャンとして生きる歩みについて十分考慮していませんでした。今までの自分の生き方のままで、イエスに「どこまでも」ついていけると思っていました。しかし、イエスについていくとは、イエスに従い、イエスと同じように歩むことなのです。
2. 躊躇する弟子
さて、続いてもう1人の人がイエスのもとにやってきます。彼は先ほどの律法学者とは反対の状況であったと言えます。つまり、イエスに従うことが、どれほどの犠牲を伴うかをよく理解していた。それだけに従っていくことを躊躇している。 彼は、イエスに従う前に、父親を葬りに帰ることを許して欲しいと言っています。ところがイエスは「わたしに従って来なさい。死人たちに、彼ら自身の死人たちを葬らせなさい」(22節)と言われました。すなわち、「あなたは今、私に従いなさい」と言われたのです。
イエスはもちろん、親不孝を勧めたり、人の死を軽視する方ではありません。同じマタイの福音書15章3-6節では十戒の第五戒を引用しつつ「父と母を敬え」という原則を教えていますし、友人のラザロが死んだ時には涙も流されました(ヨハネ11章35節)。しかし、今回の弟子については、今従うべきとのチャレンジをされたのです。それは、おそらくこの弟子の心の中の問題があったからでしょう。この弟子の心のうちは書かれていないので定かではありません。しかし、彼が何らかの理由をもって従うことを遅らせようとしたことは確かです。「イエス様、確かに私はあなたに従いたいと思っています。でも、もう少しだけ ——父親の問題が解決するまで —- 待ってください。そしたらその後に、喜んで従いますから。」
彼は、イエスに従っていくことを、恐れたのです。躊躇した。父を葬りたいという思いが偽物だっと考える必要はないでしょう。父のことを思っていたはずです。しかし同時に、イエスに従って生きていくことの困難さも予想していた。これは簡単な歩みではない、と。もしかすると自分の大事なものを手放さなければならないかもしれない。そこまでの決心は自分にはないかもしれない。だから、「父親を葬る」という “正当な” 理由をもって、従うことを遅らせようとしたのです。「将来的には、きっと私も従います」と。
私たちもこの弟子と似たようなことはないでしょうか。「いつか」「そのうち」といいながら、自分のことは棚上げにしながらキリスト教について学んだり、イエスに従うことを後回しにしてしまう。キリスト教信仰は盲信ではありませんから、よく考え、検証し、疑問を持ってもよいのです。しかし同時に考えなければならないのは、「いつか」とは一体いつのことでしょうか。どこまでわかったら、あなたは従えると思えるのでしょうか。期間の長い、短いは人によって違いますし、もちろん早ければ必ずしも良いというわけではありません(先ほどの律法学者のように)。しかしどうであっても、実は私たちはいつもイエスに「従う」か「従わない」のどちらかを選択しているのです。保留というのは、今の時点では従わないことを選んでいるのと、結果的には変わりません。
そして「いつか」という時が必ず来るという保証は、実はありません。将来の機会は訪れないかもしれないのです。それは私たちにはわからないことです。ですから、もしイエス様に従って生きていくことの困難を想定して躊躇しているならば、今、踏み出して従う決心が必要です。地上で生きる限り、全く困難がなくなることはあり得ないからです。一つ解決したかと思えば、次の困難が現れる。だから「今、従うこと」が大事だとイエスは言われたのです。
3. イエスに従う
さて、今日見てきた2人の人物は、信仰に関して対照的な問題を浮き彫りにしています。律法学者の方は、感情的には熱意に燃えていましたが、イエスに従うことに伴う犠牲を、ちゃんと考えていませんでした。無知だったわけです。おそらく彼は、イエス様の奇跡に感銘を受けて、自分もそれに参加したいと考えたのでしょう。しかし、福音の中心は、奇跡や力ではありません。信仰は問題解決のための手段ではない。それは、イエスとともに永遠のいのちに生きることに付随することに過ぎないのです。この律法学者は、真の弟子として、イエスに従うことに伴う困難を、ちゃんと考えなければならなかった。
2人目の「弟子」は、弟子として生きていくことに伴う犠牲を、より現実的に理解していました。彼がイエスに従うことを先延ばしにする理由は正当にも見えます。しかし、すでに弟子としてイエスを知っていた人であるからこそ、今、従うことが求められたのです。
イエス様に従うクリスチャンは、この両方から学ぶ必要があります。つまり、イエスに従って生きるとはどういうことかを現実的に考えるのです。信仰とは、現実的なことです。理想論や浮世的なことではない。つまり、この世と調子を合わせるのではなく、神のみこころに従ってこの世で生きるのです。それはさらに大きな視点、永遠にわたる大いなる恵みがあるからこそです。
信仰とは、現実の中でこそ磨がれていくものです。頭や心の中だけの理想郷ではない。私たちの生きる現実 ——家族との関係、職場でのあり方、隣人との会話の中でこそ、問われていくこと。それがイエス・キリストと共に「生きる」ことです。
この2人のこの後の顛末について、著者のマタイが沈黙していることは考えさせられるのではないでしょうか。つまり、私たち自身が、問われているのです。あなたは、どのように応答するでしょうか。